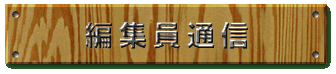
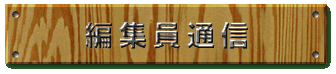
“やがて菊花賞は2流のレースに?”
|
99年まで、菊花賞の日程は11月の10日前後に組まれていた。そこへ向けた旧4歳馬は9月20日前後の神戸新聞杯、及び朝日チャレンジC、10月20日前後の京都新聞杯の両方、あるいはどちらかのひとつを踏み台に選んで本番に臨むのが通例だった。 アメリカに比べると日本に三冠馬の少なかった要因として、高温多湿の夏場を中に挟み、その過ごし方が難関とされていたことが上げられる。ダービー後を放牧など完全休養に入っていると、すっかり解放感にどっぷりと浸って緊張することを忘れ去ってしまう。再びギラつくような闘争心を呼び戻させるにはかなりの日時を必要とする。残暑厳しい中で、日々の積み重ねにより強化されて行く調教によって、馬自身が出走するレースの近づいていることを察知し本能的に精神を高揚させて行く。 3000mという未知の距離を、悔いなく戦い抜かせるには、スタミナ面の強化はことに大切。息遣いの楽な状態も普段以上に心掛けて作ってやらねばならない。稽古だけでは仕上げ切れない部分が当然あるだろう。それについては実戦を使うことによって補って行くしかない。緒戦(神戸新聞杯)が駄目でも、2戦目(京都新聞杯)で帳尻を合わせることのできた以前のように悠長に構えていられなくなった現在、本番に向けてのローテーションの選択肢は極端に狭まった。そのお陰で、神戸新聞杯の顔ぶれは3歳のトップクラスが居並ぶようになるわけだが……。 菊花賞を従来通りの価値感で見る限りでは、秋の立ち上がりを失敗すると取り返しのつかないことになってしまう危険性がより高まったといえそうだが、クラシックレースではあっても、最高賞金で実質日本のレースの中では頂点に位置づけられたジャパンCへの露払いという、重みの薄れたレースに追いやられて行きつつあるようにいたく感じ始めた。その僻んだ眼で眺めるならば、京都新聞杯は施行日を春季に左遷され、菊花賞も2週間前へと前倒しされ、レース体系の根幹も改革変容を遂げつつある。同時に、それを抵抗なく受け入れられるような我々自身の意識改革も求められているのだろうか。“主催者の決めたことだ、ゴチャゴチャ言わんと従え”と言っているように聞こえる。最近耳も遠くなり、聞き間違いかも知れないが。 編集局長 坂本日出男 |
![]()
copyright(c)NEC Interchannel,Ltd/ケイバブック1997-2001